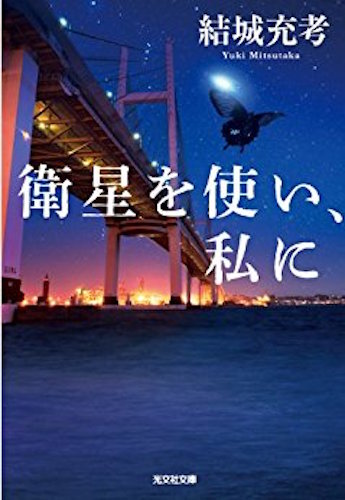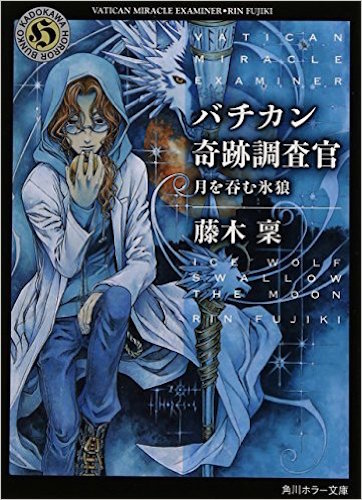
キリスト教カトリックの聖地バチカン。
主人公の平賀とロベルトは、バチカンの「聖徒の座」に所属する神父で、「聖徒の座」はキリストにかかわる奇跡の認定をする機関であり、二人は奇跡調査官として世界中から報告される奇跡の真偽の調査にあたっている。
平賀は科学者として科学的見地から、ロベルトは古文書と暗号解読の専門家として奇跡を検証する。二人は天才的な頭脳と行動力を持って奇跡とされる現象を調査しその裏側に隠された事件や陰謀をあばいていくというのが物語の主軸となっています。
世界中に教会のあるカトリックだけに舞台もアメリカ・アフリカ・イタリア・メキシコなどなどいろんな場所に及びます。起こる奇跡や事件は、まさにXファイルばりの不可解なものばかり。
腐らない死体・死者の蘇り・吸血鬼・降霊会・宙に浮く十字架などなど・・・
謎解きで明らかにされるトリックは、かなり大胆で大規模な物もあり、平賀はさらっと解明してみせるのですが、そんなことほんとに可能なの???ってのも少なくありません。また、ロベルトの暗号解読も叙事詩や古文書を天才的記憶力と発想により読み解かれるもので、いずれも読者自身が推理小説のように謎解きができる要素はなく、主人公が謎を解いていく過程を楽しみ、大胆なトリックに驚くといった感じで、この物語は平賀とロベルトの奇跡調査をめぐる冒険譚といえるでしょう。
更に、バチカン内部の派閥争いと陰謀や、世界的秘密結社の謀略、FBIなどが複雑に絡み深い謎が根底に流れていると感じさせる物語が展開します。
一話ごとに奇跡や事件の事象は、ロベルトの検証や平賀の再現実験により一応の解決をみるのですが、所々で姿をあらわす謎の組織イルミナティとジュリア牧師、姿を消した天才ハッカーのローレン、ある事件との関わりにより左遷され監視下に置かれるFBI捜査官のサスキンスなどなど、事件を追うごとに謎がますます増えていく感じ。
遺跡や教会、古城などの調査では、ロベルトの天才的な暗号解読によってインディージョーンズばりの危機からの脱出やお宝発見など冒険アクション的要素もあったりします。
現在11巻まで出版されていて、タイトルの「月を呑む氷狼」は8巻です。10巻までの大人買いをして、コツコツ読み進めて1年ほどで8巻まで来ました。
ライトノベルの様に一気読みができる内容ではないので、1巻読んでは時間をおき、気が向けば次に手を伸ばすって感じです。
で、「月を呑む氷狼」なのですが・・・
この物語は、直接の奇跡調査ではなく、友人であるFBI調査官のサスキンスの関わった事件に協力するお話。
「ラプラスの悪魔」6巻で関わったゴーストハウス事件により閑職に追いやられたサスキンス捜査官は、状況打開の相談を当時知り合ったウォーカー博士に持ちかけようとするが相手にしてもらえずにいた。しばらくするとエリザベートという女性を通じて秘密裏に博士からの連絡を受ける。女性とのデートを装い極秘回線を通じてやり取りをするという。博士とサスキンス捜査官は、ゴーストハウスの件で当局の監視下に置かれている状況で直接接触することは危険な状態にあるらしい。自分の状況に半信半疑ながらも博士の提案を受けサスキンス捜査官は博士と協力体制を取ることになる。
そんな状況の中、サスキンス捜査官はノルウェーの田舎町にある国際的企業の研究施設に発注したソフトウェアの受取に行くよう命じられる。その街に到着するやいなや空が真っ赤に染まり月が消失するとうい怪奇現象に遭遇し、さらに部屋の中で氷づけになり死亡するという不可解な事件に関わることになる。
受取場所の研究施設に赴いたサスキンス捜査官はそこでジュリア司祭そっくりの人物を見かける。そして、この地で何らかの謀略が進行していることを確信する。ジュリア司祭の捜査を盾にノルウェーにしばらくとどまることを上司に認めさせ、奇跡調査のエキスパートである友人の平賀とロベルトに協力を依頼する。

今回は、北欧神話が題材となる回です。北欧神話での終末を表すラグナロク。ラグナロクを思わせるような赤く染まる空、暗闇、空に浮かぶ炎、月の消滅。時を同じくして起こる密室での氷づけ死体。伝説の狼・氷狼の目撃談。老女が紡ぐ叙事詩に秘められた謎。
北欧神話にまつわる不可解な謎を平賀とロベルトが解き明かす。
その先には、国際的企業の研究施設がなぜこの田舎の地に施設を作ったのか?ジュリア司祭の真の目的は・・・と裏に隠された事実が明らかになっていく。
最終的には、ロベルトが聖杯にからむ古城の謎を解き明かし聖杯とおぼしき秘宝を探し当てるが、お約束どおりジュリア司祭に踊らされジ・エンド。聖杯の真偽は闇の中。